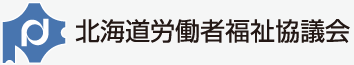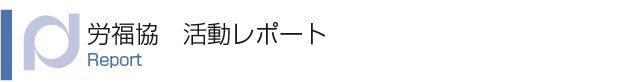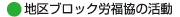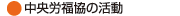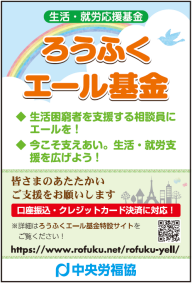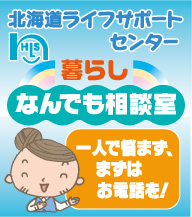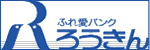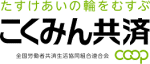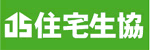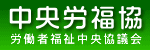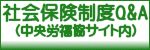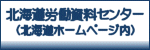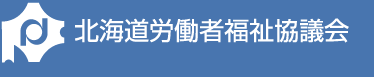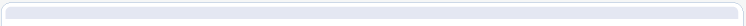
2025年7月7日
独言居士の戯言(第385号)
北海道労福協政策アドバイザー(元参議院議員) 峰崎 直樹
新連載「21世紀の証言」始まる、『週刊東洋経済』7月12日号
『週刊東洋経済』7月12日号から「21世紀の証言」という新連載がスタートした。一人の登場人物が4回にわたって「証言」するようで、第1回目として宮内義彦オリックス シニア・チェアマンが登場している。
第1回目、宮内義彦氏「規制改革責任者」としての12年間を語る
宮内さんは「規制改革」の顔として活躍され、行政改革の責任者として担当された12年間に実感したのは、「日本人は改善ができても改革ができない」とのこと。第1回の表題は『合理的に進まない改革 抵抗はすさまじかった』とあり、1995年村山内閣の行政改革委員会規制緩和小委員会に参与として参加され、翌年座長となって12年間の長きにわたる規制改革の責任者を担当されてきた。まさに、「ミスター規制改革」といってよいだろう。今企画による4回にわたっての「証言」でどのようなことが飛び出してくるのか、注目したいと思う。というのも、小生が参議院議員として1992年に国会で議席を得た時、規制緩和(改革)問題が政治の世界で大きな問題となったわけで、それをどのように総括しておられるのか、個人的にも大変興味深い問題でもあるからだ。
利害関係者の猛烈な抵抗、「改善」はできても「改革」は困難
95年に最初に手がけたのが「出版や新聞の再販売価格維持制度」であり、さらに「日本版金融ビッグバン」だったが、関係業界からは相当の反発を受けたことを吐露されている。気になったのは、厚生労働分野における規制改革問題について、改革内容を提言する前に「葬られるか、提言の内容が縮小されるかして、業界、族議員、行政によって阻まれた」し、既得権益の壁は強く、大きく動かすことができなかったとのこと。また、独占力の強いNTT、電力なども不十分な変革になってしまった、とその当時の利害関係者の動きが綴られている。
結果として宮内さんは、日本人は「改善」はできても「改革」ができないとされ、明治維新や敗戦時を除いた「平時」において、「社会、経済の動きに合わせ、制度、規則を柔軟に変化させる政治の強さが何より求められる」と述べておられる。
与党の一員としての意思決定の場、党内の合意は不十分だった
考えてみれば、90年代半ばから自民党の1党支配が崩れ始め、55年体制で対立していた自民党と社会党が政権与党を構成していたわけで、明治維新や戦後改革に匹敵するような政治の力には程遠く、改革には力不足だったのが現実だろう。現に、当選したばかりの1年生議員の小生ですら、村山自社さ政権の一員として与党の正式メンバーで参加できたのだ。ちなみに、当時の与党の政治勢力として、社会党と新党さきがけ、そして自民党で構成されていたが、課題別に自民3名、社会2名、さきがけ1名という布陣で、当時の社会党内の意思統一などが事前に十分に行われたとは言えず、政治の力不足を露呈させてしまったことは、今考えてもお粗末でしかなかったことに恥じ入るばかりである。
こうした証言でいえば、日経新聞の日曜版の2面でもテーマ別に展開されており、歴史的に貴重なものになっている。これからの展開に注目していきたい。