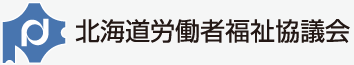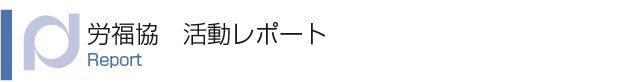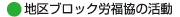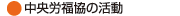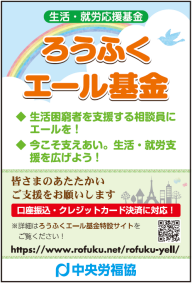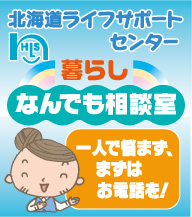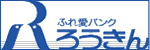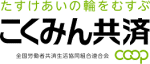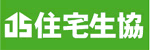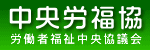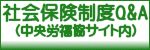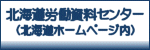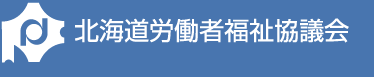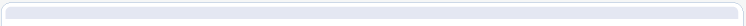
2025年9月16日
独言居士の戯言(第389号)
北海道労福協政策アドバイザー(元参議院議員) 峰崎 直樹
「ヒグマとの共存」、山際寿一前京大総長の貴重な提言
北海道に住んでいると毎年ヒグマの人的被害の報道に接する。今年もまた例年以上に被害者が出たようで、その対策に行政を始め関係者の努力が注がれるが、広大な北海道に住む野生動物であり、集落から一歩入った野山の中でいつでも遭遇する危険性があるわけで、畑の野菜や果物をはじめ、人への被害も毎年出てくるわけだ。どうしたら良いのか、一般的には畑や民家周りに電気柵を付けたり、クマよけの笛を吹きながら山道を歩くことも実施されたりしてはいるものの、相変わらず田畑の野菜や果物だけでなく、ヒグマに襲われ命を落とす人身事故が多発している。私自身北海道に住んで半世紀経つが、幸いなことに山道でヒグマに遭遇したことはいまのところまったく無い。
「ゴリラと付き合うにはオスと仲良しに」が通用しなかった現実
そんな時、「ヒグマとの共存」について、京都大学前総長で霊長類学者の山際寿一氏が、先週11日付の朝日新聞「科学季評」欄に「近づく人間 『常識』の危うさ」と題するコラムを掲載されている。山際氏は北海道知床半島での痛ましい事故が起きたことに関連して、自身がアフリカのガボン共和国でゴリラに襲われた体験に言及。ゴリラの生態についての実地調査されていた時のことだ。山際氏にとって、ルワンダやコンゴで永年ゴリラの観察をしてきた「経験知」として、「ゴリラの群れと付き合うにはオスと仲良くなればいい」と思っておられたという。というのも「メスは後ろからオスをけしかけるが決して単独では襲ってこないという自信があった」と信じておられたわけだが、ガボンのゴリラは違ってメスが襲ってきたとのことだ。
経験や常識が通用しないことが起きる地球世界の現実に目を
山際氏は総括的に次のような指摘をされ、読者に向け注意を喚起されている。
「私たちが陥りやすいわなは、過去の経験や常識に基づき判断してしまうことだ。野生動物、とりわけ大型で寿命の長い哺乳類は一筋縄ではいかない。彼らは長い一生の間に状況に合わせて独自の経験を積み学習している。その動物についてどんなにたくさんの情報を集めて常識をこしらえても、それに反する出来事が起こる」
近づき過ぎたり、えさを与えたりすることはとんでもないことなのであり、アフリカの国立公園内ではガイドがルールをしっかりと守って案内してくれるが、畑や人里に出てきたゴリラに対して、銃をはじめあらゆる方法で追い払うとのこと。そのほうが人とゴリラ双方にとって安全なのだそうだ。なるほど、それこそが合理的な生態系維持の方法なのかもしれない。
何事も過信せず、常識すらも疑いつつ行動することの重要性
最後に、山際教授は次のような提言をされている。これから知床を目指す人たちに、山際教授の提言をしっかりと認識して欲しいと思うばかりである。
「ヒグマの魅力を尊重しながらも人との共存を図る上では、国立公園と人里とで異なる対処をするべきだし、ヒグマに常識は通用しないことを肝に銘じるべきだろう」
何事も過信してしまうのではなく、常識が通用しないこともあり得ると思いながら行動していくことの重要性を痛感させられる。