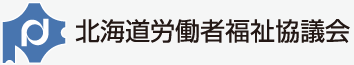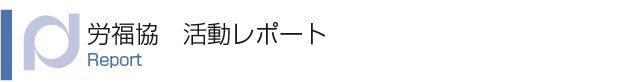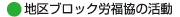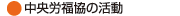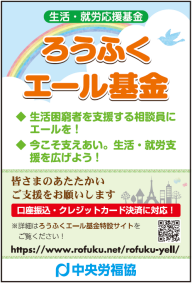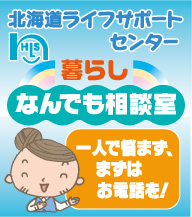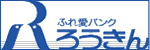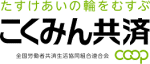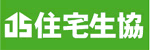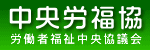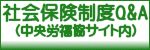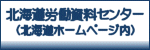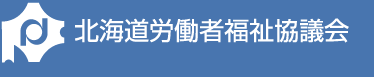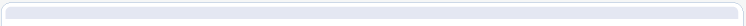
2024年12月2日
独言居士の戯言(第367号)
北海道労福協政策アドバイザー(元参議院議員) 峰崎 直樹
黒田前日銀総裁、異次元の金融緩和の『失敗』に触れない講演録
財務省が発刊している月刊誌『ファイナンス』が、毎月我が家に送られてくる。2024年10月号と11月号に黒田東彦前日銀総裁が、母校の東京大学で講演された議事録「財政金融政策に関する私の経験」(前編と後編)が掲載されている。いうまでもなく黒田前総裁は財務省出身であり、前編は主として財務省での経験が、後編で日銀総裁時代が取り上げられ、東大生の前で実にわかりやすく話をされている。すでに、日本経済新聞の「私の履歴書」欄でも自身の経験されてきたことを率直に語っておられるわけで、それ程目新しいことが書かれているわけではない。ただ、自身が日銀総裁となられて2期10年間、「異次元の金融緩和」政策が幾多の変遷をたどりながらも、日銀が政府と約束した2%という消費者物価上昇率目標が2年以内に実現できなかったことに対する「総括」が十分になされているとはいえず、いくら東大生を前にした経験談とはいえ「反省」は「反省」としてきちんと総括するべきではないかと思えてならない。
「2年で2%物価上昇を2倍の貨幣増加で実現」できなかった理由?
というのも、就任時に大量の貨幣を市場に提供してインフレ「期待」を醸成すれば、2年で2%という目標を実現できると豪語していたにもかかわらず、2年経っても実現できず、結果として「イールドカープコントロール政策」への転換やマイナスの金利の導入などを余儀なくされ、当初の意気込みとは裏腹に最後は精彩を欠いたまま2期10年まで勤め上げ退陣されるに至ったわけだ。ただ、総裁を辞める1年前ぐらいからインフレが進み始めたものの、日銀の異次元の金融緩和による国民の「期待」の変化としての成果が上がったというよりも、海外からの石油価格の上昇や急激に進んだ円安(これは内外金利差の拡大で生じた面があり日銀のゼロ金利政策が影響している面がある)によって進んだことに触れ、自身が総裁を退任した後にようやく植田新総裁の下で金融政策の正常化が進んだ経緯について、この間の経過を知る者にとって拍子抜けするほど実に淡々と述べておられ、違和感を禁じえなかった。
「期待」に働きかけた異次元金融緩和は物価上昇とは無縁、失敗だ
問題は、自身が総裁就任時に提起された異次元と名づけた金融緩和政策によって「期待」(何故か、この掲載紙には「合理的期待」という一般的な表現ではなく「適合的期待」とある)に働きかけたにもかかわらず、なぜ2%という目標に達することができなかったのか、という点にあり、それが実現できなかった要因として消費税の引き上げや外的な要因を上げておられるだけで、「貨幣数量説」に依拠しながら、国民の持つ根強いノルムとなっていた「デフレ持続」から「インフレ期待」に働きかけた日銀の異次元の金融緩和政策が誤っていたのではないか、という点の踏み込んだ問題点には全く触れておられないのだ。黒田前総裁と岩田規久男副総裁(その後、新しき審議委員になられた方達は、いわゆる「リフレ派」であった)が安倍総理から就任を要請された際、自信をもって2年で2%の達成を高らかに謳ったことへの反省の弁はない。本来であれば、1期5年の任期で辞任すべきだったのだろう。ところが、異次元の金融緩和の下で国債の大量発行を進めた安倍政権にとって、日銀の取ったこうした政策は誠に好都合だったわけで、その齎した日本経済への悪影響は膨大な財政赤字の累積となって、大きなダメージを与えることになるのは必至だ。
吉川洋東大名誉教授の異次元金融緩和策への鋭い批判、日銀には働きかけるマクロの「期待」は存在しない
こうした経済政策について、先週号の『週刊エコノミスト』(2024年12月3日号)が経済政策についての特集を組んでいて、興味深い指摘が満載されている。
黒田前総裁が進めてきた「異次元緩和」に対して真っ向から切り込んでおられるのが、吉川洋東大名誉教授であり、「異次元緩和の壮大な社会実験は米国主流派経済学による実害だ」と題するインタビュー記事の中で、黒田日銀の取った異次元の金融緩和政策に対して次のように批判される。
「異次元緩和は、家計や企業といった経済主体は将来につき合理的期待を形成するというルーカス理論に基づく、日銀が家計や企業に2年で2%インフレになるように通貨供給量(マネタリーベース)を2倍に増やすと宣言したのが当初の異次元緩和だった。しかし、期待インフレといっても企業経営者が将来予想する期待インフレと、主婦のそれとは違うのは明らかだろう。企業経営者なら原材料費や自社製品の販売価格がどうなるのか。主婦なら日々の食料品価格といったように関心を持つ物価の対象が違う。日本全体の代表的『期待インフレ』などない。企業経営者も主婦も消費増税には高い関心を示すが、日銀のマネタリーベースは知らない。日銀には、期待に働きかける対象が存在しない」(前掲書37頁より)
ルーカス・シカゴ大教授の「合理的期待形成理論」の過ちを継承した異次元金融緩和政策
吉川教授は、ケインズ経済学を批判しその後の主流派経済学をリードしてきたシカゴ大学教授ロバート・ルーカスの「合理的期待に働きかける経済学」を批判され、その流れを汲んだのが異次元の金融緩和政策なのであり、大失敗となって今の日本経済があることを痛烈に批判されている。さらに、こうした主流派の経済学がリーマンショックを経てその理論が破綻しているにもかかわらず、日本をはじめ拡がっているのは、専門家として評価される学術誌にはこうしたアメリカの主流派に属する論文しか掲載されなくなっている現実を指摘する。これをどう是正させることができるのか、問題の根源はなかなか難問となって迫ってくる。
門間一夫元日銀理事、「異次元金融緩和は失敗」だったとバッサリ
私が注目しているエコノミストに門間一夫氏がいる。門間氏は日銀出身で、いまは「みずほリサーチ&テクノロジーズ」のエグゼクティブエコノミストをされている。その門間氏が書かれた『門間一夫の経済深読み』と題する電子版月刊コラムの11月27日号で、「異次元緩和の総括は終わらない~副作用の歴史的評価はずっと先~」を掲載されている。
いろいろと興味深い指摘がされているのだが、異次元の金融緩和政策について、次のように指摘されている。
「異次元緩和は『2年程度で2%物価目標を達成する』ために導入されたのであり、そのミッションに失敗した事実は導入2年後の2015年4月に確定している。この明快な評価軸に照らせば異次元緩和の効果はなかったのであり、それ以上の議論は時間の無駄である」と実に明快である。
金融政策は成長戦略たりえない事が明確に、異次元金融緩和政策の徹底化がもたらした効果???
もっとも、それでは身もふたもないので、その齎した功罪など、いろいろと指摘されてはいる。特に、円安の問題など金融緩和と為替相場の問題などは今後議論していくべき重要な論点として提起されている。と同時に、この間の金融政策について「金融政策には限界があり成長戦略の代替にはならない」と人々がはっきり認識できるようになったことの意義が大きいと指摘し、その意味で「異次元金融緩和を徹底的にやって『良かった』と思う」と見ておられる。元日銀マンとしての率直な感想を吐露されたものといえよう。それは、異次元金融緩和の弊害が門間氏の「見立て」では財政や生産性に悪影響は与えていなかったのではないかとみておられるからである。はてさて「見立て」が正しかったと言えるのかどうか、なかなか経済の見方にはいろいろとあるのだと痛感させられる。
【門間一夫氏の電子版コラムのURL】
https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/executive/pdf/km_c241127.pdf