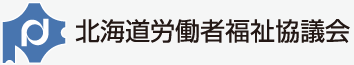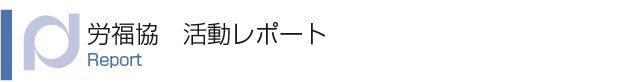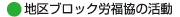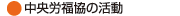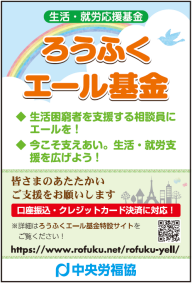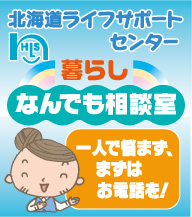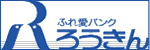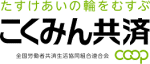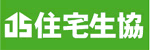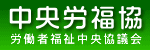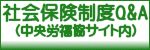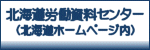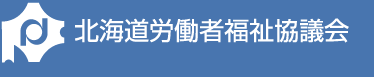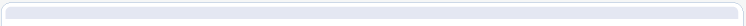
2025年2月25日
独言居士の戯言(第375号)
北海道労福協政策アドバイザー(元参議院議員) 峰崎 直樹
約1か月間の休刊のお知らせ、体調不良で入院治療に専念したい
体調を崩し、今週末から入院して治療に専念せざるを得なくなってしまった。常日頃の不摂生がもたらしたものであり、いつもこのニュースレターを読んでいただいている皆様方に、約1か月近い休刊をお願いすることになる。3月末には再び発信できるよう準備をしていきたいと思うのだが、いずれにせよ1か月近い情報ブランクになるわけで、準備ができ次第再開させていただきたいと思うばかりだ。
最近の立憲民主党は元気がなく、存在感が乏しくなっていないか?
最近の日本の政局を見た時、石破少数与党政権の下で野党第1党である立憲民主党の存在感のなさが気になって仕方がない。野田代表は、実に温厚な態度で少数与党である石破政権に対して穏健な態度で対応してきておられる。日本維新の会や国民民主党が、政権与党側との政策実現に向けた激しいやり取りが、国会論戦はもとより水面下での与野党交渉の前面に出ているわけで、その存在感の無さが党内外からも漸く指摘され始めている。野田代表が真っ先に衆議院の予算委員会で、今までの野党が常に進めてきた「日程闘争」を封印する「武装解除」を宣言したわけだが、今ではそれが仇になって最大野党の立憲民主党の存在感を喪失させてしまっていることは明らかだろう。
相手の石破政権が過半数を持っていないわけだが、与党として野党の一角を取り込んで国会運営に全力投球していることは明らかであり、今からでも遅くない、政権交代を目指して国会内外での戦いの先頭に立って多数派を形成すべく努力して欲しい。今の段階では、維新が教育予算や石油価格の引き下げと引き換えに予算の賛成に立場を変えたようだが、どうすれば野党が一丸となって政局を転換できるのか、なかなか良いアイディアがあるわけではないものの、何とか知恵を絞って欲しいと思うばかりである。
物価上昇率にも追いつかない賃金引上げ、定昇は賃上げではない
経済に目を転じてみたい。われわれ国民の生活を悪化させているインフレが進み、最新の物価上昇率は昨年12月の対前年比3.0%の引き上げとなっている。昨年の春闘での賃上げは名目で定昇込み5%程度でしかなく、中小企業などではそれ以下の賃上げで、定昇分約2%を考慮すれば3%を下回るわけで、日本の労働者の賃金は3年前の春闘からは名目で2~3%引き上がったとしても、実質的には1年前に比較してマイナスとなってしまっている。それだけ、経営者側の取り分が増え続けているわけだ。
河野龍太郎著『日本経済の死角—収奪的システムを解き明かす』を読んで
ここで考えてみたいのは、なぜ日本の労働者の賃金が上がらなくなってしまっているのか、という点である。最近話題を呼んでいるエコノミスト河野龍太郎氏の書かれたちくま新書『日本経済の死角—収奪的システムを解き明かす』を読み終えて、日本の定期昇給制度が主として大企業では適用されているわけで、その定期昇給額は1.5~2%程度であり、90年代半ばからここ2~3年前までベアが無かった時代でも定昇額分だけは上がり続けてきたことに着目しておられる。この点は、既に昨年出版された浜口桂一郎氏の書かれた『日本の賃金』(朝日新書)で述べておられることからの引用であり、改めて日本の労働者の賃上げがここ30年近く引き上げられなかったことの要因として述べておられるのだ。
定期昇給が存在するから賃上げができていると錯覚する労働者
定期昇給なる物は、年功賃金として毎年定期的に昇給するカーブを描いた道をたどっているわけで、賃銀水準はそのカーブを辿るだけで賃金水準全体は何の引き上げもなされていないのだ。かつて、最初に就職した鉄鋼労連時代に賃金調査部に配属され、基本給や職務給、更には能率給などの仕組みを知った時、鉄鋼労働者の賃金は定期昇給がある基本給は3分の一程度で、職務給では職務が上位等級に上がらなければそのままで、能率給に至っては能率が上がらない限りはこれまた上昇しなかったことを知り、ホワイトカラーや公務員給与などは大半の賃金(給与)が定期昇給によって上昇していくこととは異なっていたことを印象深く記憶させられてきた。
今、日本の労働者の賃金がお隣の韓国や台湾などと比較しても下がってきていることを知るわけだが、こうした日本の大部分の労働者の賃金決定の在り方を変えていかなければ、本当に劣悪な賃金に据え置かれ続けてしまうのではないだろうか。河野龍太郎氏のこの著書は、日本の労働者の賃金がなぜ上がらないのかを含めて、是非とも多くの働く労働者に読んで欲しい一冊である。