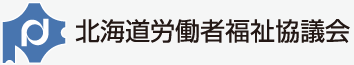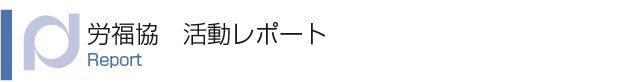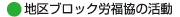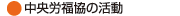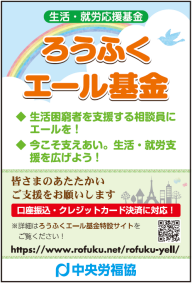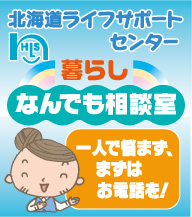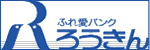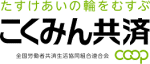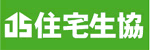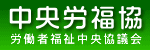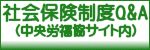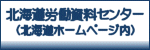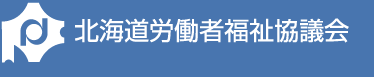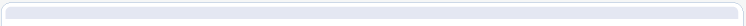
2025年4月21日
独言居士の戯言(第376号)
北海道労福協政策アドバイザー(元参議院議員) 峰崎 直樹
参議院選挙の争点、消費税減税についてどう考えるべきか
国会が閉じると3年に一度半数改選する参議院選挙が待ち受けている。衆議院では与野党は逆転、少数与党で石破政権は綱渡りだが、参議院では過半数を自公で確保しているだけに、その行方が注目されるのは当然だろう。
選挙となれば当然のことながら争点が明確になるわけだが、与野党の中から出始めているのが個別政策課題でいえば「減税」であり、特に物価上昇に苦しむ国民向けに「消費税の減税」が浮かび上がりつつある。特に野党側は立憲民主党を除いて消費税減税を打ち出し始めており、立憲民主党内でも減税派と据え置き派が併存し、党内論争が活発になり始めているようだ。
立憲民主党が国民民主党の後塵を拝している支持率の低下に注目
4月22日号の『週刊エコノミスト』誌に、人羅格毎日新聞論説委員の書かれたコラム「東奔西走」欄「政界に広がる相互関税ショック 野田・立憲に重たい消費税問題」に注目した。
人羅氏は世論調査の結果で見て、昨年の選挙以降、立憲民主党の支持率が国民民主党よりも低くなっている事を取り上げ、その要因として第一に「ネット戦略」の欠如を、第二に「国民生活に寄り添う目玉政策の不在」をあげておられる。特に、野田代表の消極的な姿勢について問題視されており、党内にある消費税減税を巡る論戦をどう進めていくのか、トランプ関税など経済が不安定化するなかで石破政権が消費税減税を打ち出してくれば、立憲だけが取り残されるわけで、場合によっては大連立政権すら考えられる時代に向かうこともあり得るとまで言及されている。昨年総選挙以降の支持率が低迷し、国民民主党の後塵を拝する立憲民主党にとって、今の段階で政治的に考えるべき点を鋭く指摘されている。
立憲民主党内で波紋を呼ぶ枝野最高顧問発言、支持の広がりは?
こうした中で、立憲民主党創設の立役者である枝野幸男最高顧問の発言が党内に波紋を投げかけている。報道によれば、4月12日さいたま市内の講演で、党内で消費税減税の意見が相次いでいることに対して「減税したい人は諦めてもらうか別の党を作って欲しい」と述べたとのこと。また、「財源を明確に示さないのは国民生活にとってマイナスだ」「ポピュリズムに走らない。減税といっても票になるわけない。立民はぶれてはいけない」と、党内で進められている参議院選挙公約で「消費税減税」に待ったをかけようとしているとのことだ。
このやや「上から目線の辛口発言」は、立憲民主党内で江田憲司元代表代行らが飲食料品の消費税率を「物価上昇率が続く当分の間、ゼロ%にすべきだ」と主張していることへの批判のようだが、江田議員の提言は党内でかなりの賛同を得ているとのことだ。
飲食料品の消費税率の引下げは「逆進性の効果」が無いのでは
ところで、「飲食料品の消費税率を下げる」ことでどんな効果があるのだろうか。一般的には飲食料品は国民の生活にとって不可欠なもので、貧困層ほどエンゲル係数が高くなるわけで税負担軽減効果を持つのではないかと思われているが果たしてそうなのだろうか。現に2019年度から飲食料品を10%から8%へと下げたわけだが、そのことによって逆進性が緩和されたという実感が語られることは少なかったのではないだろうか。税制は「簡素・公平・中立」という大原則の下で何よりも国民にわかりやすく、複雑な制度にすべきでないことは言うまでもない。富裕層も飲食料品の軽減税率の適用を受けるわけだから、それほどの効果がもともとあるわけがないのだ。
税の原則として「簡素・公平・中立」、複雑さは避けるべきでは
私自身が議員時代に消費税率の引き上げに直接タッチした時、特にこの「簡素・公平・中立」原則に強くこだわった事を思い出す。ひとたびこの原則がねじ曲がると、そこから次々に原則が乱れ始めることを危惧し続けてきた。さらに、一度下げた税率を再び引き上げることの困難さにも注意する必要がある。さらに、これは税制の専門家である東京財団の森信茂樹氏がヨーロッパの実例について指摘されていることなのだが、果たして法律で消費税率を下げたとしても、現実には下げないことがありうるわけで、消費者がそれを見抜くことの難しさも考えるべき点なのだろう。
消費税の重要性は財源調達力にあり、その財源で再分配強化へ
こう考えてくると、軽減税率や0%税率への引き下げなどという事に拘泥するよりも、得られた税収をどう社会保障や教育を軸にした再分配財源に振り向けられていくべきなのか、使われ方にこそ関心を向けるべきではないだろうか。安易に選挙目当ての消費税減税は、「百害あって一利なし」と見るべきだ。日本の財政赤字が危機的なレベルにあるだけに余計そう思うのだがどうだろうか。
【ちょっと気になった報道】
18日の毎日新聞社会面で、毎年春と秋に実施されている園遊会の進め方が変更されるとの報道(「園遊会に新風『脱一列』両陛下と皇族別ルートで」)に接した。議員時代に何度か参加したことがあり、内外の有名人や各界の功労者の方達が参加され、天皇皇后をはじめ多くの皇室の方達が赤坂御苑での饗宴を主催される。今までは皇室の方達が一段となって参加者の方達に順番に回られたわけだが、これからは天皇皇后と秋篠宮など分かれて参加者との懇談をされるとのことだ。招待者の「待ち」緩和が目的とのことだ。
なにげない記事ではあるが、ひょっとすると将来的には興味深いものへと変わる可能性があるのではないかと思えてならない。というのは、皇室の方達の中で「誰が一番人気がある」のか、それが参加者の方達によって選別が進むこともあり得るのであり、ひいてはこれからの皇室の在り方にまで影響が及ぶ可能性すらあり得ると見たのだがどうだろうか。
とはいえ、そこは宮内庁が仕切るわけで、参加者の配置が偏らないような配慮をするのだろうが、誰がどの皇族とお会いしたいのかまで統制することはできまい。この改革がどんな結果をもたらすものなのか予断を持つことはできないが、皇室の在り方に一つの波紋を投げかけていくのではないかと思うのは思い過ごしだろうか。
報道によれば、陛下はこの改革に前向きだと言われており、22日の園遊会から実施されるとのこと。国民と皇室の触れあいを通じて、皇室に対する親しみが増すことに期待したい。