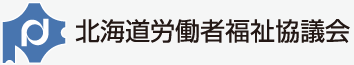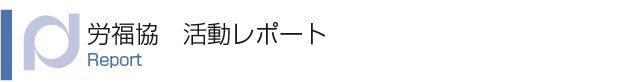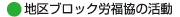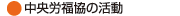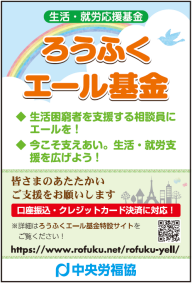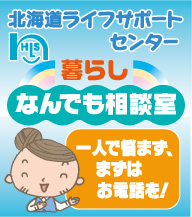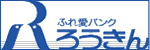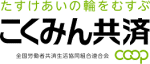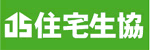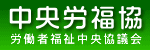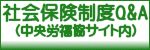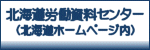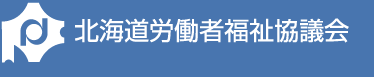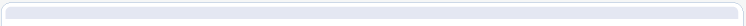
2025年5月12日
独言居士の戯言(第378号)
北海道労福協政策アドバイザー(元参議院議員) 峰崎 直樹
5月連休により、時間の余裕ができたので、積読していた本を読むことができた。今回は、ミアシャイマーシカゴ大学教授の『リベラリズムという妄想』にチャレンジしてみた。国際政治をどう考えていくべきなのか、やや異端派に近いミアシャイマー氏とのことではあるが、なかなか興味深いものであったことは確かである。
書評『リベラリズムという妄想』ジョン・ミアシャイマー著
(新田享子訳 伊藤貫解説 経営科学出版 2024年刊)
通説とは異なるウクライナ侵攻の捉え方、ミアシャイマー教授に注目
ロシアによるウクライナ侵攻という事態をどう捉えたらよいのか、国際法に違反した侵略だという意見が世界的にも大半を占める中で、注目したのが今回取り上げたジョン・J・ミアシャイマー氏の見解であり、ロシアに一義的な責任があるのではなく、むしろアメリカをはじめとする西側(NATO)にこそあるという見解を披歴してきた。ミアシャイマー氏は、シカゴ大学教授として半世紀近く国際政治を研究してこられたわけで、今までも多くの論文を執筆され、世界的にも注目される論客であることは間違いない。もっとも、この分野におけるミアシャイマー氏の立ち位置は異端派であり、アメリカの政治学会に関する主流派からは事実上排除されていたとのことだが、そのあたりはこの本の解説を書かれている国際政治アナリスト伊藤貫氏の巻末の解説が詳しい。
私自身、こうした国際政治については殆んど門外漢であるだけに、どれだけ的確に内容を理解できているのか自信は無いのだが、以下、門外漢なりにミアシャイマー著『リベラリズムの妄想』についての読後感を書いてみたいと思う。
なぜ冷戦以降、アメリカ外交は悲惨な失敗を累積し続けたのか
ミアシャイマー氏がこの本を書こうと思った動機について2つの視点を上げている。
一つは、冷戦以降のアメリカの外交政策が何故時に悲惨な失敗を招くのか、特に中東での失敗を取り上げている。
二つには、リベラリズム・ナショナリズム・リアリズムの3つの見方がどのように関わり合って国家間の関係に影響を及ぼしているのか、ミアシャイマー氏自身はナショナリズムが強い影響力を持つと考えていたが、アメリカの2001年以降の外交の失敗の数々がうまく説明できると考え、この二つの視点を取り上げて「リベラリズム」の持つ問題点をあらゆる角度から指摘されている。
「リベラル・ヘゲモニー」を目指せば世界はどうなっていくのか
ミアシャイマー氏は、まず「リベラル・ヘゲモニー」という概念を次のように提起する。「ある国ができるだけ多くの国を自国のような自由民主主義国家に変えながら開かれた国際経済の促進や、国際機関の構築を目指す野心的な戦略」で、要は強大な力を持った自由主義国家が自らの価値観を世界にあまねく普及しようとする戦略の事であり、そのような国が「勢力均衡を重視する政治をめざさずに、リベラル・へゲモニーを追求した場合、何が起こるのだろうか」と本書での狙いを明らかにしている。つまりアメリカは、冷戦後においてリベラル・ヘゲモニーによって自分たちの思惑で世界を作り替えようとしてきたわけだが、ミアシャイマー氏はそれらが失敗する運命にあり現実に失敗してしまったと述べている。
アメリカの齎した国際的な災厄、リベラル・デモクラシー追及の結果だ
というのも、「この戦略は、最終的にリベラリズムよりも国際政治にはるかに大きな影響力を持つナショナリズムやリアリズムと対立する政策を生むからだ。しかし、これは大半のアメリカ人にとって受け入れがたい事実なのである」(6~7p)と指摘し、これからのアメリカ外交について「ナショナリズム」や「リアリズム」に基づいて進めていくべきことを進めているのだ。
ところが、冷戦以降アメリカはリベラル・デモクラシーを追求し、クリントン、ブッシュ、、オバマ時代にリベラルの拡大に突き進み、特にブッシュ政権時代にはイラク侵攻から中東へと戦火を拡大させ大混乱を招いてきたことを指摘する。いまや中国の台頭やロシアの復活によってアメリカ一国の時代から複数の大国との対峙を迫られているわけで、リベラリズムからリアリズムへと戦略の切り替えが求められていると提起する。
リベラリズム評価、国内政策と国際的レベルでは質的に異なる
ミアシャイマー氏はリベラリズムを敵視しているのではなく、国内と国際制度内とできちんと区別をしておく必要があり、国内でのリベラリズムは望ましい政治イデオロギーだが、国際レベルでは別物で、効果は出てこないどころか国内にまで悪影響を及ぼすことを指摘する。それは、国内においては政府が存在して様々な利害集団のコンフリクトをそれなりにコントロールできているわけだが、国際社会では実質的な世界政府が存在していないわけで、国際法規が支配する世界とはいえ、今眼前に進められているロシアとウクライナの戦争にみられるように、それぞれの国のむき出しの利害対立がまかり通ってしまうからに他ならない。外交努力による一定の規制はあり得るのだが、それらの効果は残念ながら国内法に基づく物とは質的に劣ることは間違いない。リベラリズムはナショナリズムと絶えず共存する必要があり、ナショナリズムと衝突すれば必ず敗北することとなる。
ナショナリズムの強固さは歴史的にも実証済み、労働者階級の国際的連帯の蹉跌
ナショナリズムの強固さは、マルクス主義の世界でも実証済みで、かつて第2インターナショナル時代に労働者階級が第1次世界大戦で階級間の国際的な連帯よりも、それぞれの国のナショナリズムを優先したことが指摘されている。それは、ナショナリズムがリベラリズムよりも人間の本性に合致しているからだとミアシャイマー氏は見ている。さらに、自由主義的政治制度を持った『世界国家』は生まれる見込みはなく、強大なアメリカですら一度も世界全体を俯瞰できる国家を目指そうと仄めかしたことすらない。かくして、国際的な無政府状態が続くわけで,諸大国はリアリズムによって行動するしかない。生き残るにはそれしかなく、リベラリズムには国際政治に当てはまる政策は上手くいかないのだ。
ミアシャイマー氏の提言、ナショナリズムに立脚し、リアリズムに基づいた「節度ある外交」を
最後の「第8章抑制のすすめ」に於いて、今後のアメリカの外交政策に対していくつかの提案を打ち出している。
第一に、アメリカはリベラル・ヘゲモニーの追求という壮大な野望を捨てるべきだ。失敗しやすく戦争に巻き込み、結局「敗北」をする。
第二に、アメリカ政府はいくら策略を巡らそうとしても「ナショナリズム」によって現実的な策略になることを肝に銘じたうえで、リアリズムに基づいたもっと節度のある外交政策をとるべきである。そのほうが、「アメリカが関わる戦争の数は減り、外交努力が実る機会が増えるだろう。そこへナショナリズムが加われば、海外で野心的政策を展開する必要性はさらに減る。要するに、アメリカは自制の美徳を学ぶべきなのだ」(420p)と提起しているのだ。
ミアシャイマー氏はリベラル・ヘゲモニーから脱却して現実主義的な対外政策をとる可能性について、次の2点次第だとみる。
一つは国際制度の将来の姿、将来の世界勢力図。
もう一つは、なかなか理解が困難なのだが「外交政策を選択するにあたって自由主義国家が持っている主体性と自由の度合いである」と述べている。
中国の台頭にどう対応していくべきか、リベラル・ヘゲモニーの放棄に行き着くのでは
最後にミアシャイマー氏が述べているのが中国の台頭という時代において、大国中国には「競争」関係が、中国が衰退の兆しを示し始めてくればアメリカが再びリベラル・ヘゲモニーに戻ってしまうのではないかと予想されている。そして、失敗の経験を積みながらやがて「リベラル・ヘゲモニーという欠点の多い戦略を放棄するだろう」(422p)と期待しておられる。
少し気になったのは、自由主義国家は、特にエリート層には「十字軍的な衝動が深く刻み込まれていて、世界を自由主義に塗り替えようとせずにはいられない」からリベラル・ヘゲモニーを追及するのだという指摘があるが、東洋人にとってはなかなか理解しにくい点なのかもしれない。