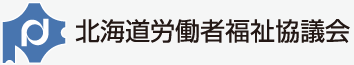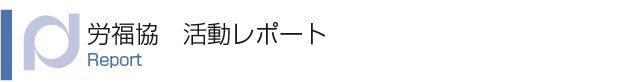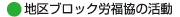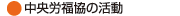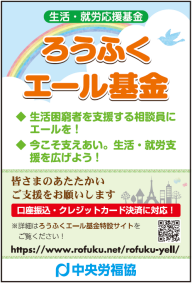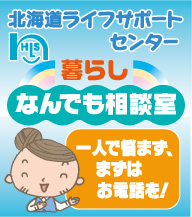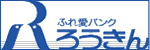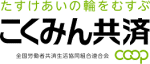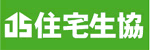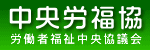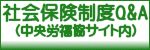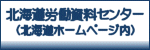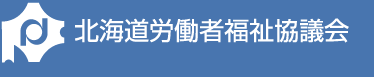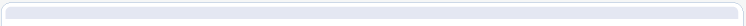
2025年5月19日
独言居士の戯言(第379号)
北海道労福協政策アドバイザー(元参議院議員) 峰崎 直樹
7月参議院選挙の争点、消費税減税に進む野党と与党の対立
7月の参議院選挙を前にして、立憲民主党が消費税率を食料品に限って1年間ゼロ税率に引き下げを打ち出してきた。これで、野党側はすべて消費税率の引き下げに向けて足並みをそろえたことになる。与党側の自民党内においても、選挙を前にした参議院サイドから消費税率の引き下げの要望が出ているようだが、自民党の森山幹事長や宮沢税制調査会長ら幹部は消費税率の引き下げに応ずることはなさそうだ。
特に、幹事長の森山裕氏は野党側が打ち出している消費税減税に関して「政権を奪取するための甘い話」であり、「自民党幹事長として政治生命をかけて対応したい」と厳しい対応をとることを地元屋久島で言明へ。消費税を誕生させたときの自民党の税制調査会長が、同じ鹿児島県選出の先輩代議士山中貞則氏だったこともあるのだろうか。かなり力が入っていることは確かだ。そういえば、鹿児島県選出の野党社会党書記長の久保旦参議院議員が、消費税導入時の反対の急先鋒だったことを思い出し、鹿児島県人の熱の高さにやや驚いたことを思い出す。
税制こそは国の成り立ちの基本であり、安易な政治判断は過ちへ
一度下げた税率を再び引き上げるためには大変な政治的エネルギーを要するわけで、1989年に消費税が導入されて以降の歴史を見れば、今の10%(食料品は8%)に至るまでの政治の現場での与野党の攻防が、安易な税率の引き下げを躊躇させるものがあるのは頷ける。自民党の政権政党としての矜持を感じさせられた動きとして、与野党の政党関係者はよく理解しておく必要があると思うのは小生だけだろうか。税は国の基本であり、その基本原則として「簡素・公平・中立」の持つ重要性は政治の基本中の基本なのだ。
立憲民主党の消費税減税は苦渋の選択だろうが、党体質の露呈か
野田立憲民主党代表も、かつて与党時代に消費税を社会保障財源として位置づけ、10%へと引き上げてきた責任者だっただけに、最後まで消費税減税に言及してこなかったわけだが、選挙を前にして党内の強まる消費税減税の声を無視しえなかったのだろう。ここにきて減税へと踏み込まざるを得ない発言となったようだ。その根拠たるや、これまでの言動からは一歩距離を置かざるを得なかったことは間違いない。苦渋の選択とは言え、立憲民主党の体質の限界が現れたものと観たがどうだろう。「給付付き税額控除」の具体化にむけ知恵を絞った方が良いのではないか、と思うのだがどうだろうか。
消費税の社会保障財源化で合意できていたのではなかったのか?
消費税率の引き下げを求める根拠として、この間の物価の上昇による生活費の高騰を挙げる人が多い。確かに物価の上昇による価格引き上げ分はそのまま消費税に跳ね返るわけで、税率を引き下げて欲しいという声が上がるのもムベなるかなではある。消費税は税率1%で2.7兆円の税収があるわけで、日本の財政の基幹税としての消費税の果たしている大きな役割にこそ目を向ける必要があるのだと思う。所得税の最高税率1%の引き上げはせいぜい100億円単位であることと対比して欲しい。
1989年の消費税導入以降の歴史を見るにつけ、民主党政権時代に消費税率の10%への引き上げに舵を切ってきたわけで、年金、医療・介護、子育てなど社会保障財源に充てていくことを法定化したことでその位置づけは明確になっている。社会保障財源の引き上げが論議されるとき、その必要財源としての消費税の引き上げも同時に解決していくべきであろう。
基幹税としての消費税、西欧では20%台にまで引き上げへ
今の10%の税率は、ヨーロッパを中心に20%近い税率(デンマークなどでは25%)にまで引き上げられているわけで、これから社会保障制度の拡充が求められるときには、まだまだ国民の負担能力の範囲内にあり、不可欠な税制として位置づけられよう。所得税と並んで消費税が日本の税制の中で30兆円近い税収を占めており、基幹税として大きな役割を果たしていることを見失ってはなるまい。問題は税の使われ方の問題にかかってくるのだ。
消費税の軽減税率は何のためにあるのか、逆進性緩和に役立たず
消費税は、低所得者でも高所得者でも同じ価格の商品を購入すれば同じ税率がかかるわけで、所得税のような累進性(所得の高さに応じて税が逓増する仕組み)を持たない。にもかかわらず食料品については軽減税率8%という複数税率が適用されているわけだが、高額所得者にまで同じ軽減税率が適用されることから低所得者層だけに有利な仕組みにはなっていない。つまり、軽減税率にする積極的な意味がないわけだ。
所得税の累進課税もあまり機能していない日本の所得税制の限界
では、累進制が導入されているとされる所得税が果たしてどのように機能しているのだろうか。所得税には、課税最低限が設けられ、一定金額以下の所得には税がかからない。さらに、基礎控除や扶養者数などによって所得控除も設定されている。だが日本の場合、所得が勤労所得や雑所得は合算されても、株式配当や利子所得など金融所得などが分離されているため、総合課税とはなっていない。そのため、金融所得が大きな収入を占めておられる高額所得層には有利になっているわけで、マイナンバー制度が導入された今、銀行や証券口座など資産性(金融)所得との紐づけをすすめて総合課税へと転換させていくことを強く主張したい。所得税の部分的な累進性があることでもって所得税の方が公平・公正な税制だと理解する向きもあるが、総合課税化が進んでいない日本においては、それほど公正さを発揮することになっていないことを理解しておくべきだ。
所得、消費だけでなく、資産課税強化に目を向ける時ではないか
じつは、所得税の世界だけではなく、資産課税、とりわけ相続・贈与税においてもマイナンバーの紐づけが求められるべきだろう。日本の社会が徐々に高齢社会へと移行しつつあり、フローの所得も重要ではあるが、ストックとしての資産のウエイトが高くなっているわけで、見逃すことのできない論点であることは間違いない。
それにしても、所得・消費・資産のそれぞれの分野に関する税制がバランスよく機能してこそ「公平な税制」として国民に受け入れられるのではないだろうか。今後の税制の動きに注意深く観てきたい