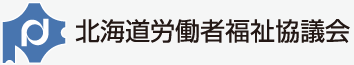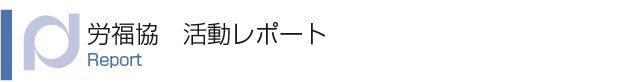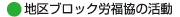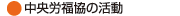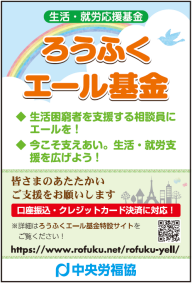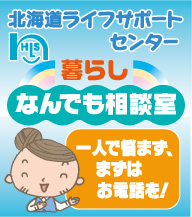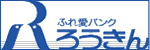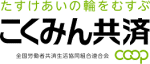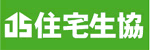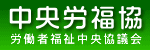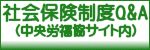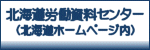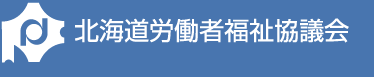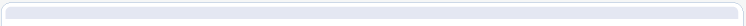
2025年5月26日
独言居士の戯言(第380号)
北海道労福協政策アドバイザー(元参議院議員) 峰崎 直樹
米中関税抗争は常識的なレベルまで引き下げへ、トランプ流か?
トランプ大統領の発動した共通関税政策は、最も親しい同盟国であるイギリスを最初の交渉相手として進め、次いで最も厳しい対応を取った中国との間においても、両者それぞれ張り合っていた「常識外れの高関税率」から115%の引き下げによって、対中国30%、対アメリカ10%という常識的なレベルへの低下となって事が進み始めた。今後日本との間でどのような交渉が進められていくのか、やがて90日間の時間の猶予の終了後の7月初旬には明らかになるのだろう。7月初旬といえば、参議院選挙の公示日になるわけで、選挙の大きな争点にまでなる可能性がある。。
こうした動きの中で、毎週のように日本経済が抱えている問題についての野口悠紀雄一橋大学名誉教授が書かれている『東洋経済オンライン』での論文が参考になる。最新の5月25日号で「『関税戦争』沈静化でホッと一息→いやいや、それは平和ボケだ!ビジネスパーソンが今こそ警戒すべき中国の”新たな経済戦略”」というちょっと長いテーマの論文を寄稿されている。野口教授は、トランプの進めた中国とのやり取りを通じて彼の進めている「強硬な関税政策の限界」が明らかになったとみておられる。
中国のグローバル経済主導権確保に向けた新しい戦略の採用へ
この論文でちょっと驚いたのは、中国はアメリカに対して選挙区事情を精密に分析したうえでの「精密報復」を実施している事。さらに国際的な面での「経済圏の多極化を志向する戦略」を並行して進め、ASEAN諸国や「一帯一路」構想を通じた経済連携強化をすすめ、アメリカ依存を相対的に低下させると同時にグローバル経済における主導権確保へと進み始めているとのことだ。詳しい動きについては当該論文を読んでいただきたいのだが、野口教授が注目されているのが「デジタル経済やグリーン経済における中国主導の標準設定」の動きだ。「5Gインフラ」「AI」「再生可能エネルギー」といった分野で国際標準の策定を通じた影響力拡大を目指しており、アメリカとのし烈な覇権争いが進むとみておられる。かくして、米中の対立の軸は「単なる関税戦争から、より深層の技術・ルール・基準の争奪戦へと移行」しているとの見立てだ。この動きが今後どう展開していくのか、注意深く見ていく必要があることは間違いない。
基軸通貨ドルを抱えたアメリカの悩み、第2のプラザ合意へ
さて、アメリカの動きに焦点を絞ろう。
アメリカが抱えている問題は、結局は基軸通貨ドルが抱えている問題となって「ドル防衛」を進めようとしていることにあるとみていいのだろう。今から40年前の1985年、アメリカの抱えた巨額の財政赤字の累積とドル高の是正に向けて、先進5か国の財務大臣らがアメリカのプラザホテルに結集して協議した問題の再燃だとみていい。トランプ政権が抱えている問題も、結局は基軸通貨ドルを抱えているが故に生じているわけで、トランプ政権の大統領経済諮問委員会(CEA)委員長スティーブン・ミラン氏が進めている次のような新しい経済政策の採用が提起されようとしているのだ。
ドルや円、ユーロ、人民元などの通貨相場を人為的に多国間で協調介入に踏み切り、ドルの高騰に歯止めをかける。「プラザ合意2.0」とも「マールアラーゴ合意」とも呼ばれる構想を2024年秋に唱え始めた張本人がミラン氏だ。
アメリカ国債格付け、ムーディーズもAAAからAA格へ引き下げへ
彼は、「トリフィンのジレンマ」という考え方に依拠しており、「基軸通貨は国外でも広く使われ、需要が高まる結果、相場が割高になる。自国通貨が割高になると輸出競争力は落ち、貿易収支は赤字に陥りがちだ。覇権国の赤字で世界が栄えるほど基軸通貨の需要は高まり、相場がさらに上がるスパイラルにはまる」というもので、ベルギーの経済学者ロバート・トリフィンが提唱した考え方である。今のアメリカにおいて、ドルの決済や投資、準備資産の中心という基軸通貨の地位を保つには、ドルを潤沢に国外に供給し続ける必要があるわけで、アメリカが慢性的な経常赤字と財政赤字という「双子の赤字」を抱えることで成り立ってきたわけだ。今回、アメリカは、こうした基軸通貨国としての抱えざるを得ない役割を世界は理解して支え合っていくべきことを求めているわけだ。最近のアメリカ国債の格付けがムーディーズによってAAAからAAへと格下げられ、最上級の格付けから陥落したことが象徴しているように「ドル離れ」が進展していることを市場シグナルが発信している。
経済だけでなく、軍事的安全保障でも応分の負担が求められる
経済だけの問題ではなく、安全保障に関しても基軸通貨国は弱点を抱えやすくなるとみており、日米安全保障条約によって日本を防衛していることへの相応の負担を求めてくることも十分に想定されるわけで、これからのトランプのアメリカが何をどうするのか、経済だけでなく安全保障面での動きからも目が離せなくなってきている。
【お願い】
今まて560号まで発刊することができました。ひとえに、皆様方のおかげだと感謝いたしています。少し体力は回復しつつあるのですが、まだ本調子ではありません。すこし、休刊させていただいて、また気力・体力を充実させたうえで再開させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。